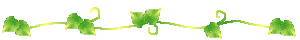
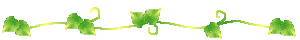
|
★このコース三年振りの実施です。斎王の群行が午後1時に開始。見学する為に斎宮歴史博物館で昼食をとり、時間を調整して頂く。 斎王まつり斎王群行画像
|
 斎宮のハナショウブ群落 斎宮のハナショウブ群落★今回は池一面ハナショウブ見事に開花しており、華やかさはありませんが、落ち着いた雰囲気を醸し出していました。またこの池の奥側の場所ににショウブがギッシリと植栽されており、次回の例会の折には花を楽しめるかもしれません。  斎宮歴史博物館 斎宮歴史博物館★斎王まつり期間中とあって当博物館まえ広場には露店や歌・太極拳・踊り等々のアトラクションがあり大変賑わっていました。年々「おまつり」が華やかになって来ており人々の流れも多くなって来ています。  上園芝生広場 上園芝生広場★今回は見学時間を充分取って頂いたお蔭で斎王群行をユックリと見ることが出来ました。平安時代の雅な衣裳を身にまとって群行にまるで平安時代にタイムスリップしたようは気分に陥る。 近鉄四日市駅----松阪駅----明星駅----菖蒲群生地----隆子女王の墓----斎王の森----斎宮歴史博物館----漕代駅
|