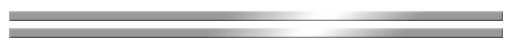津田学園高校野球部物語
第一章(平成3年初夏から8年夏)
平成3年6月に軟式野球部から硬式野球部となった。当時の須賀副校長(現津田体育専門学校校長)に軟式野球部員が懇願し誕生した。しかし、実際に活動を始めると道具はなく、練習も野球経験者がほとんどおらずキャッチボールもできない状態であった。部員たちは「どうしても夏の大会に参加したい」ということだったので、恥を覚悟で加盟申請を行ったという。それからが大変であった。須賀先生が近隣高校から使わなくなった道具・ボールなどを譲り受け何とか練習ができる環境ができた。そうこうしている間に夏の大会抽選会の日となった。キャプテンがくじを引いた。そうすると「何と!」運が良いのか悪いのか開幕試合を引き当ててしまったのだ。ここで初めてマスコミから注目を集め、学校にも取材の申し込みなどがあり、学校側も何とか恥をかかないようにと、職員の中から野球経験者を集め、急遽大会に向けての本格的な練習が始まった。しかし、満足にキャッチボールもできない選手がいくら努力しても限界がある。大会に向け場慣れするためにも試合をということで四日市四郷と東員町野球場で練習試合をやって頂くことになった。素人軍団と試合をして頂いて本当に感謝感激であった。結果は予想通り5回コールド19対0であった。しかし、当時の練習をみている限りでは、ほんの2週間の練習であったが成果は表れていた。そして開会式を迎えた。当時のユニホームはオーソドックスな白と黒のものであり、いかにも弱そうな感じがした。開会式が終わりいよいよ試合開始となる。相手は名張西である。先頭打者が打ち上げた。その瞬間目を疑ってしまた。平凡なセンターフライにもかかわらず、中堅手は全く動けない。あとは想像通り一方的な試合展開となった。相手に失礼にならないように選手たちは全力でプレーはしていたが、如何せん初心者の集まりで本当にかわいそうになった。しかし、コールド間近の5回、何と2点タイムリーが出て完封負けを免れた。この2点こそがホンの短い間の練習であったが、選手たちの努力の賜ものであった。17対2(5回コールド)負けはしたが、1・2年生がほとんどでこれからが楽しみであった。この試合は三重テレビで放映されており、多くの人々に津田学園高校に野球部ができたということもそうだが、学校自体の存在もアピール出来た。現に中澤監督もこの試合を偶然見ており津田学園を知ったという。また、現コーチの林大士もこの大会、三重高校の選手として出場していた。今、思うと何か因縁めいたものがあった。 しかし、大会が終了すると選手の多くがグランドから足が遠のき、開店休業の状態が続いた。
平成4年新学期を迎え津田学園高校に本格的に野球をやっていた教員が赴任した。中澤良文(三重高校―法政大学出身)である。しかし、学校はなにも野球を強化するつもりはなく、たまたま中澤先生が野球を経験していただけのことであった。当時高校教員で野球を経験している教員はおらず、中澤先生が監督となった。しかし、中澤監督は希望に燃えていた。小さい頃からの夢が実現したのである。そして、グランドに出た。高校・大学と一流の施設・選手とやってきただけに、津田学園の現実を目の当たりにして呆然となった。道具・用具がほとんどない。際たることに選手までもがいなくなっていた。急遽 部員の勧誘を行ったが、2名の入部しかなかった。1期生の伊藤健治と上別府孝であった。この時からが本当の始まりであった。練習も思い通りにできず、大変な苦労を選手はしたが、監督が母校に合同練習を申し込んだりして、少ない人数ながら辛抱した。この年の大会は当然のことながら辞退となった。しかし、監督は練習と並行して、秋から選手勧誘に奔走した。
平成5年、待ちにまった春を迎えた。新入部員を迎え入れ野球がようやくできるようになったのである。しかし、2年生2人、1年生数名の若いチームである。投手も上別府1人しか投げることができない。練習試合も1日1試合のみで、連戦は不可能であった。当然試合相手もなかなか見つからず、辛い日々が続いた。たまの練習試合でも経験の少ないチームは、ボロボロの展開となり途中でタオルを投げた試合もあった。当時は本当に相手高校にもご迷惑をかけていた。しかし、この悔しさをバネに選手達は猛練習に歯を食いしばって耐えた。夏の大会前には、何とかなりそうなところまで上達した。その成果は初戦で表れた。朝明高校に7対4で勝利したのだ。ほんの一年前までは、試合もできなかったチームが初勝利を収めたのだ。この勝利は監督、選手のひた向きな練習の成果であった。しかし、3回戦で力尽きた。秋の大会では経験者がそのまま残り県大会に初出場を果たした。1期生2人を中心にまとまりのあるチームに成長していた。初戦、牟婁地区の1位校尾鷲と対戦し延長の末勝利して、続く津東にも快勝した。ベスト8進出である。次の対戦相手は監督の母校三重である。気合を入れて望んだが、何せ相手は三重県代表する伝統校である。結果は大敗であった。しかし、がんばれば不可能を可能にできることが身をもって実感することのできた大会でもあった。その冬からは、本当の意味で甲子園を狙う猛練習の始まりでもあった。
平成6年4月を迎えた。この年の新入生は桑員・三泗地区から10数名の入部希望者が集まった。選手たちをみて、監督は「甲子園出場」が近い将来に実現する予感があったという。ようやく3学年そろい、本格的に練習・練習試合もできるようになった。そしてこの年の新入生は4月から試合に出場できるぐらいの力もあった。春季大会もベスト16を果たし、夏の大会に期待が膨らんだ。そうして向かえた夏の大会では、選抜大会ベスト4の桑名西高校と対戦することになる。負けて当たり前の試合であったが、奇襲攻撃が功を奏して中盤まで食らいついて善戦をした。しかし、後半突き離され敗れてしまった。この試合を最後に1期生2人は引退した。(上別府は社会人野球トヨタ自動車に入社)新チームとなり更なる飛躍を決意した秋の大会も善戦むなしく敗退した。ここからの冬の練習は創部以来、一番辛く長い練習が行われた。グランドも中澤監督が照明を設置した。帰宅時間も11時ぐらいになることも多々あった。練習帰りに不審者と間違われパトカーに止められたこともあったという。そのような練習に耐え切れず退部する者も多くいた。十数名いた1年生も春には11名となっていた。この春休みは、冬の練習の成果を試すために、徳島池田高校に遠征した。この年は阪神淡路大震災の影響で、和歌山からフェリーを使う強行行程であり、池亀運転手に大変なお世話をかけた。
平成7年 春。この年ぐらいから近県の学校とも頻繁に練習試合をして頂けるようになってはいたが、当時はまだ専用グランドもなくスクールバスを借り、運転手 瀬戸口さん 松井さん 酒井さん 池亀さんのご協力で多くの試合を経験できた。また、ゴールデンウィークの連休を利用して広島県まで遠征試合も行った。監督の夏に掛ける思いがそこにはあった。そして、夏の大会を向かえた。「今大会こそは」という思いとは裏腹に、初戦 津工業に序盤から大量リードを奪われた。コールド負け寸前に、入学から下積みの仕事をよくがんばった根本和門を代打に送った。その根本の根性のヒットから始まり、厳しい冬の練習を耐え抜いた2年生たちが繋いで大量点を奪った。試合は1点差で敗れはしたものの「最後まで諦めなければ何とかなる。」ということが、身を持って感じられた試合でもあった。また、厳しい練習があったからこそできたことでもある。この敗戦が新チームに大きな財産となった。新チームになり練習試合も近県のみならず近畿地方まで足を運んだ。結果は上々であった。エースには、1年生から投げていた陣田匡人(中京大―現ミキハウス)がケガから復活して、捕手は主将の藤田久也とバッテリーを中心に小細工の利く嫌らしいチームが出来上がっていた。秋の大会桑員地区予選では桑名西に初めて勝利して1位代表で県大会に出場した。当時はまだ決勝リーグでベスト4のチームが東海大会の代表権を争った。日生第二、津商業に勝利して創部以来初の決勝リーグ進出を果たした。四日市工業、伊勢工業、菰野が残ったが、初戦の伊勢工業にはコールド負けを喫した。続く菰野との対戦は雨の降るなか善戦はしたが惜敗した。後がなくなった四日市工業に勝利したが1勝2敗。そして四日市工業との3位決定戦となった。接戦となったが、選手一人ひとりの精神力で勝てた試合であった。初の東海大会出場である。夢の甲子園が手に届くところまできた。この年は三重県で開催され、地元の球場で試合ができる大きなメリットがあった。1回戦は静岡2位校島田商業との対戦であった。しかし、四日市霞ヶ浦球場に入った瞬間、驚く光景が目に飛び込んでだ。相手スタンドは超満員なのである。並々ならぬ勢いが感じられた。試合が始まると序盤から点数を重ね楽勝かと思われた終盤、陣田が右肘に死球を受けてしまい腕が伸ばせない状態になっていた。しかし、陣田は投げ続けた。そのような状態では、まともに投げられず9回にはついに追い詰められてしまった。失策も出てしまい最悪の状態ではあった。チーム全員が耐えに耐え勝利することができた。チーム一丸とはまさにこの時のことであった。しかし、陣田の肘の状態が心配であった。2回戦は翌日なのである。森弘和か伊藤敬一の登板を予想していた。ところが、2回戦岐阜1位校中京商業(現中京)戦には陣田がマウンドに立っていた。この試合は初回の右翼手森の好返球と藤田のブロックで死守したのが大きかった。陣田も痛みを耐え絶妙の投球で点を与えず、バント、スチール、エンドラン、ホームスチールで揺さぶるこのチームの持ち味が発揮され快勝することができたのだ。ベスト4進出。甲子園が現実のものと・・・・。準決勝は愛知東邦である。流石の野武士軍団もこの試合は何か堅くなっていたような気がした。結果はよく踏ん張って僅差の敗北であったが、この時点で甲子園の夢は消えたかのように思われた。現に監督、選手は試合終了後すぐに帰宅していた。2試合目愛知大成と静岡浜松工業の試合で大成がコールドで敗れる大波乱がおこったのだ。東邦 大成 浜松工業 津田学園この中から3校選出となれば・・・。夢が大きく膨らんだ。出場校発表日が長く感じられた。発表の日 高橋校長のもとに電話が入った。夢がかなったのである。創部4年目 2人から始まった野球部が甲子園出場を果たしたのである。誰が予想したであろうか。監督はもちろん、監督を信じ己を信じ努力した選手たち、また1期生2期生の力の結晶が奇跡を生んだのだ。甲子園出場決定により学校のグランドにも黒土とマウンドが初めてつくられた。満足な練習が学校でもできるようになった。あとは選手の意識の向上である。目標設定が課題であった。今まで甲子園出場が大目標であり、それを実現したということになると目標を失ってしまう危険性が。そのあたりが少し心配であった。当時の女子マネージャー伊藤美和は練習の裏方の仕事から接客、練習のことまで細心の注意を払い選手をサポートしていた。当時2年生であった彼女は先輩が手を抜いた練習をしていると涙して訴えていた。そのようなマネージャーの存在が大きかった。
選抜大会開会式、入場行進が始まった。中澤監督となってからユニホームも阪神タイガースの生地を使わせて頂き高価なユニホームにしていた。これには訳があった。監督から聞いたことなのだが、創部当時は津田学園高校の野球部であるということが恥ずかしいと思う選手が多かったので、自信を持たせるため立派なユニホームを作ったということである。そのユニホームが甲子園球場によく映えていた。まさに感動の瞬間であった。そして3月29日、試合が始まった。相手は九州代表の小倉東である。初回に不味い守備で1点を献上する苦しい展開となったが、陣田の球はいつも以上に走っていた。ところが、攻撃はここという時に一本の安打が出ず、逆に中盤追加点を与えてしまい終盤大量失点を喫し、終わってみれば12対1。やはり甲子園は恐ろしいところだと実感した試合であった。この後、すぐに学校に戻り練習を始めた。東海地区の代表として出場したこの大会、出場しただけの大会となってしまった。春の大会に雪辱を果たすつもりで練習を行った。
平成8年4月甲子園効果もあり、新入生は30数名の入部希望者がやってきた。しかし、練習がはじまると20名弱になってしまった。この頃は積極的に新入生の勧誘を行っていなかったのだ。「春の三重県優勝」これを目標に県大会に臨んだ。2回戦では秋の大会の代表を争った四日市工業に大接戦の末勝利して、続く準々決勝、準決勝も勝ち抜いた。決勝では海星を2対0の完封で念願の優勝を果たした。このチームは本当に勝負強いところがあった。1つのアウトを無駄にしない野球ができていた。春の東海大会にも出場をするのだが、中京大中京に大逆転負けを喫してしまった。春の県大会優勝で目標を見失っていたのである。また、この試合で陣田が腰を痛めてしまい夏の大会の出場も危うくなってしまった。学校に戻るとすぐに自主練習となったのだが、悔しさも表さない選手の態度に次の日から監督が練習に参加しなくなったのだ。藤田主将が監督に謝りにいったのだが、「選手の様子をしばらく見させてもらう。」ということで聞き入れてもらえなかった。この間2年生数名の選手が辞めていった。部員が多くなり3年生と1・2年生の意識があまりにも開きがあったのである。1・2年生の勝負に対する意識が低すぎたのである。この一件以来、選手たちの意識、監督が常々言っていた「自主性」の大切さがようやく理解できてきたように思えた。試合をするのは選手たちなのだ。自分たちがやらなければ進歩はないのである。そうして、陣田のケガが完治しないまま夏の大会を迎えようとしていた。不運は続くものである。内野手の三輪宣貴までもが最終の練習試合で、手の甲を骨折してしまい満身創痍の状態となってしまった。この年の大会から4校のシード制が採用されるようになり津田学園高校は第一シード校となっていた。初戦木本との試合では、三輪が出場できず一塁手の巨漢田中寿一が三塁を守り、投手には春から成長著しい伊藤、捕手は藤田、2塁手には1年生ながら春の大会から出場している前村直哉(中京大)、遊撃手は守備に定評のあった2年生の間崎裕介(西濃運輸)、1塁手には2年生の中村広紀、外野は左翼手沼澤栄治、中堅手加藤智樹、右翼手森の布陣で臨んだ。序盤から先取点を取られ苦しい試合展開であったが、後半逆転して何とか勝利した。しかし、春の勢いは感じられなかった。次の相手は三重である。絶対に負けられない試合で陣田が登板を志願した。調子は戻らず序盤からリードを許す展開で、途中からは1年生の前村を登板させた。流れは変わり一時追いついたのだが、後半スクイズを決められ一歩及ばなかった。悔しい負けではあった。しかし、この試合は陣田にしても痛みを我慢してよく投げた。三輪も骨折をしての出場であった。その他の控え選手もそれぞれの役割を果たしていた。三塁コーチの山下誠は持病を持ちながら皆と同じように3年間がんばった。加藤弘高、児玉幸土もひた向きによくがんばっていた。3年間の集大成をこの大会で披露することができた。夏の甲子園出場は逃してしまったが、胸を脹れる内容であった。
4年前にできた普通の野球部が甲子園出場を決めたのだが、この後また苦難の道を歩み出すことになる。
第一章終了
この物語は中澤監督をはじめ学校関係者から取材をしてまとめたものである。
平成8年秋以降については、近日中に掲載する予定です。